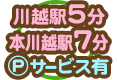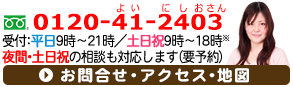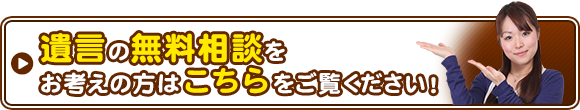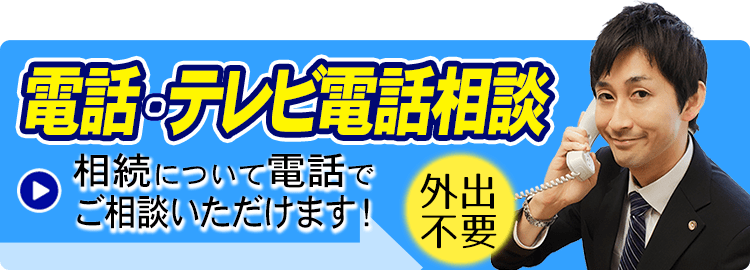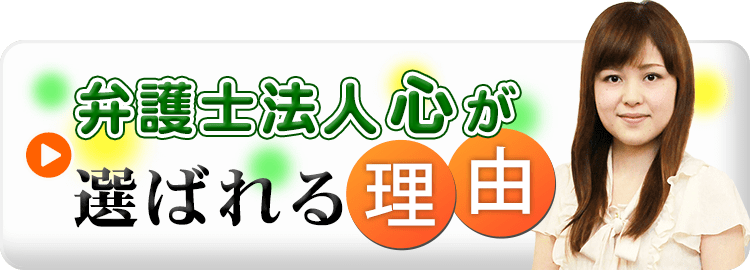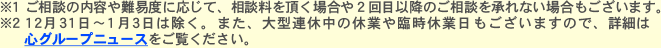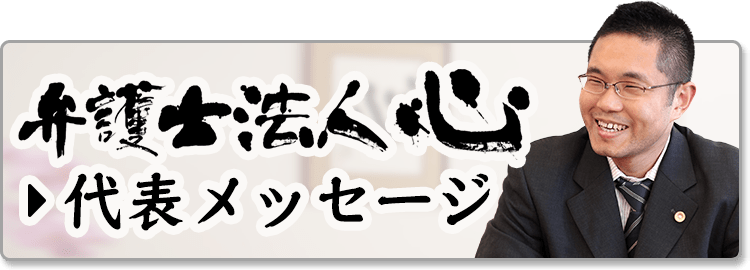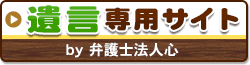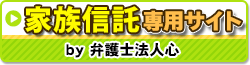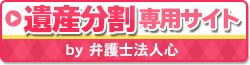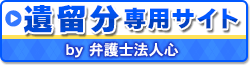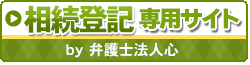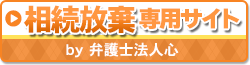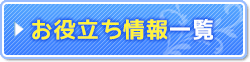自筆証書遺言で注意すること
1 自筆証書遺言作成の際に注意すべき点はいくつもあります
結論から申し上げますと、自筆証書遺言を作成する際には、次の点に気を付ける必要があります。
①厳格な形式的要件を満たしていないと無効となる可能性がある
②紛失や汚損、相続開始後に遺言が発見されない可能性がある
③原則として相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要になる
自筆証書遺言は、公証役場で公証人を介して作成する公正証書遺言と異なり、紙とペンと印鑑さえあれば、ご自身で手軽に作成できるというメリットがあります。
しかし、上述のような点に気をつけて作成しないと、遺言に記した遺志が実現されなかったり、相続人や受遺者との間での争いの元になってしまうこともあります。
以下、自筆証書遺言で注意すべき点について、詳しく説明します。
2 厳格な形式的要件を満たしていないと無効となる可能性がある
自筆証書遺言は、法律によって次のような形式的な要件が定められていて、これらの要件を満たしていないと無効になってしまう可能性があります。
①原則として全文を自筆で書く必要がある
自筆証書遺言は、遺言者自身が、自筆で書かなければなりません。
例外として、遺言の一部である財産目録はパソコンを使うこと等で作成することができます。
ただし、この場合には各ページに遺言者の署名と押印が必要となります。
②遺言を作成した日付を正確に記載する必要がある
「令和〇年吉日」と書いたり、和暦の元号を省略して書く(例えば「24年」と書くと、平成24年なのか2024年なのかがわからなくなります)ことは避けましょう。
遺言は、複数作成した場合、基本的に後に作られた方が有効となりますので、作られた日付を明確にしておく必要があります。
③遺言者の署名と押印が必要になる
実務上、遺言者の押印には実印を用い、遺言作成日に近い日付で発行された印鑑証明書も添付します。
押印に用いる印鑑には制限はなく、認印も使用可能ですが、同じ苗字の方(特に親族)による偽造が疑われることを防止するため、実印を使用した方が安全です。
3 紛失や汚損、相続開始後に遺言が発見されない可能性がある
法務局による遺言保管制度を利用しない場合には、自筆証書遺言は基本的に遺言者ご自身が保管、管理する必要があります。
遺言を紛失してしまったり、汚損してしまった場合、相続開始後に使用することができなくなってしまいます。
また、厳重に保管した結果、相続人が遺言を見つけられなくなってしまっても、遺言を使用することができません。
このような事態に陥ることを防止するためには、信頼できる利害関係のない親族や、弁護士等の専門家に遺言を預ける等の対策が必要です
法務局の遺言保管制度を利用することも有効ですが、法務局に預けたことを、信頼できる方に伝えておくことも大切です。